自分の目の前にある現実を、ありのまま受け入れるには時間がかかります。その状況に慣れることは大変なことです。悲しみに圧倒され、まるで自分の身体の一部を失ったかのように感じるかもしれません。
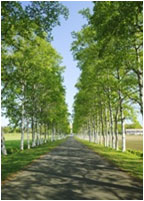 困難な時期には、毎日、自分にできることを少しずつやってみることが大切です。誰もがそれぞれの方法で悲しみ、喪失に対処します。
困難な時期には、毎日、自分にできることを少しずつやってみることが大切です。誰もがそれぞれの方法で悲しみ、喪失に対処します。
以下のことは喪失後に役立つと言われていることですが、すべてを行う必要はありません。参考にされて、ご自身のできそうなことを探してみて下さい。
【1.自分自身をケアする】
【2.現実を受け入れる】
【3.信頼できる人と話をする】
【4.自分をサポートしてくれる人を探す】
【5.そのほかに知っておいて役立つこと】
東日本大震災では、津波によって、愛する人が行方不明になった方が数多くいらっしゃいました。大切な方の存在が確認できないことは、ご家族や友人にとって非常に大きなストレスになります。その方の事をいつも考えて不安になったり、亡くなっているのではないかと気持ちが沈んだり、時には生きているはずだと思ったり、とても不安定な状態になります。また,こういう気持ちが周囲に理解されないために,「忘れなさい」、「あきらめなさい」というような言い方をされて深く傷つくこともあります。
このような行方不明者の家族の状況は、「あいまいな喪失(ambiguous loss)」と呼ばれています。アメリカのミネソタ大学のPauline Boss博士が提唱した考え方です。
 あいまいな喪失には2つのタイプがあります。一つは,行方不明のように、実際にいなくっているのに,その生死が確認出来ないような状態です。もう一つは、存在しているのに、今までと大きく変わってしまったことで心理的には喪失しているような状態です。
あいまいな喪失には2つのタイプがあります。一つは,行方不明のように、実際にいなくっているのに,その生死が確認出来ないような状態です。もう一つは、存在しているのに、今までと大きく変わってしまったことで心理的には喪失しているような状態です。
災害で大切な方の生死が確認できない状態は、①に該当します。また、東日本大震災の福島で起こった状況のように、故郷が存在するにもかかわらず、その町がすっかり変わってしまった状態は②に該当します。
あいまいな喪失には、答えがありません。誰もその方が生きているのか亡くなっているのか正しい答えを出す事が出来ません。そのような状態では、家族はその方を待ち続けるほうが良いのか、もうあきらめてしまったほうが良いのかがわからなくなります。これはとても不安定な状態です。
また、家族の中でも、ひとりひとり、その状況のとらえ方や感じ方が異なります。99.9%亡くなっているだろうと思われる場合でも、それが確認できない限り、人々は0.1%に希望を持ち、気持ちに区切りをつけることが難しくなります。また、0.1%にこだわる自分に混乱し、自分がおかしいのではないかと感じることもあります。
Boss博士は、このような状態の方にこう勧めています。「どちらかに決める必要はない」と。なぜならば、事実は誰も「わからない」からです。
しかし、「わからない」状態のまま生きていくことは、とても大変なことです。何らかの対処が必要です。
今も大切な方の存在がわからず苦しんでいる方は「どちらかに決める」必要はありません。気持ちに区切りをつけようと思うほど、つかなくなります。
現実的な問題、たとえば葬儀や死亡届を出すのかといった問題は、家族でよく話し合うことが大切です。そのとき、家族ひとりひとりの思いが異なっても構いません。状況があいまいで不確実なので、出てくる思いや考えも、人によってさまざまなのです。お互いの気持ちに耳を傾けながら、どうすれば良いかを家族みんなで模索することが大切です。
家族で、今いないその方とのつながりを感じられるようなことをすることも大切です。例えば,その方のことを家族で話したり、写真を飾ったり,その方の好きな花を飾ったりすることは,心の中でその方との繋がりを取り戻すために役立ちます。
また、同じ立場にある人や、家族や自分の思いを理解してくれる人に、今の思いを少し話してみることが良いこともあります。
あいまいな喪失への対処は、「ひとりひとり考え方が違っても良い」ということから始まります。あなたの周囲の人も、あなた自身も、そのことを認められるようになれば、互いに支え合うことができます。自分の思いが尊重されたと感じた時、人は次の一歩を踏み出せるのです。
あいまいな喪失に関しては、「あいまいな喪失情報ウェブサイト http://al.jdgs.jp/ 」を是非お読み下さい。
災害による死別は、大きな外傷体験(トラウマ)でもあります。そのような外傷体験後の回復のゴールは、死別という出来事を忘れることでも、その苦痛が二度と起こらないようにすることでもありません。何年経っても悲しみは起こるものですし、大切な人のことはいつまでも忘れることはないのです。
しかし、悲嘆(グリーフ)があまりに長く強く続くと、健康上にさまざまな問題が生じることもあります。たとえば、複雑性悲嘆やうつ病、PTSD(心的外傷後ストレス障害)、アルコール依存など、深刻な状況に陥り、日常生活に支障をきたす場合があるのです。
もしあなたが、何ヶ月間も以下のような項目が当てはまり、日常生活に影響が出ている場合には、死別に詳しい精神科医や心療内科医、心理職、かかりつけ医、保健師、死別の支援を行っている支援機関(精神保健福祉センターなど)に相談して下さい。
 感情がなくなったかのような麻痺した感覚が続く
感情がなくなったかのような麻痺した感覚が続く大切な人との死別後は、さまざまな法的な手続きがあります。さまざまな手続きは、その方が亡くなったことを実感させるため、ご家族・ご遺族にとって、大きなストレスとなるかもしれません。反面、手続きをすることで、家族が徐々にその人の死を受けとめていくプロセスになることもあります。

ここに死別後に必要な手続きを記載致しますが、一人で背負わず、信頼できる人に少し手伝ってもらうことも、自分自身をケアするという意味で大切なことです。
【死別後すぐに必要なこと】
〇葬儀社の決定
亡くなられた方とご家族の意思を、可能な限り反映して頂けるような葬儀社を選択された方が良いでしょう。事前の相談が必要な場合もあります。
〇宗教者への連絡
通夜・葬儀の日時、式場などを打ち合わせします。宗教者の助けも大切です。
〇連絡先リストの作成
交友関係を確かめるために、亡くなられた方と親しかった方にお手伝いをお願いされてもよいかもしれません。
〇通夜・葬儀の連絡
連絡をスムーズに行うため、亡くなられた方と親しかった方にお手伝いをお願されてもよいかもしれません。
【早めに必要なこと】
〇電気・ガス・水道の名義変更
電力会社やガス会社、水道局に手続が必要です。電話でも可能です。
〇運転免許証の返却
警察または公安委員会で手続が必要です。いつも身に着けておられたものですので、返却は簡単なことではないかもしれません。
〇クレジットカード
クレジットカード会社に解約の手続を依頼します。
〇遺言の確認
遺言書があるかどうかを確認します。遺言には、①公正証書遺言、②秘密証書遺言、③自筆証書遺言があります。①は公証人役場で確認する事が可能です。②③は、自宅や銀行の貸金庫、近親者のところ等で保管されている可能性があります。②③の場合は、家庭裁判所に提出し検認という手続きを受ける必要があります。
〇相続財産の確認
不動産登記簿・預金通帳・金融機関からの取引報告書などを確認します。
〇遺産相続
遺言書がない場合は、相続人全員が、民法に定める割合で相続分が決まります。しかし、相続人全員で、誰がどの財産を相続するか、話し合いで決める事も可能です。その場合は、遺産分割協議書を作成し、相続人全員の捺印が必要です。遺産分割協議書は自分で作成する事も出来ますが、司法書士などに依頼する方法もあります。遺産分割には期限がありませんが、相続税等に影響しますので、相続税の申告時期までには確定しておくことが望ましいです。
【死別後7日以内に必要なこと】
〇死亡届の提出
医師の診断書と一緒に役所に提出します。死亡届の提出後に、火葬許可申請書を提出し、火葬許可証をもらいます。なお、火葬許可書は火葬場で「火葬済」の押印をもらい、納骨の際に墓地等の管理者に提出する必要があります。
【死別後14日以内に必要なこと】
〇年金受給停止
役所または年金事務所に手続が必要です。
〇住民票の世帯主変更届
亡くなられた方が世帯主であった場合は、役所で変更手続きが必要です。世帯主の方が亡くなられて、自分が世帯主になったとき、あらためてその方がいなくなったことを実感し、いろいろな感情が湧いてくることもあります。
〇国民健康保険証の返却
役所で手続が必要です。
〇介護保険証の返却
役所で手続が必要です。
【死別後3か月以内に必要なこと】
〇相続放棄
亡くなられた方に債務(借金)がある場合は、相続放棄の手続きをすることも可能です。その場合は、相続開始があったことを知った時(通常は被相続人の死亡を知った時)から3か月以内に家庭裁判所に「相続放棄の申述」をする必要があります。その場合は、財産も相続できませんのでご注意ください。また、放棄すれば、他の相続人が債務を相続することになりますので、他の相続人も同様に手続きした方が良いでしょう。また、相続財産がプラスかマイナスか明らかでない場合は、「限定承認の申述」をすれば、相続によって取得するプラスの財産の限度で、なくなられた方の債務を支払えばすみます。限定承認は、共同相続人全員が共同で、3か月以内に家庭裁判所で手続きをします。
【死別後10か月以内に必要なこと】
〇相続税の申告・納付
税務署に申告・納付が必要です。税理士や税務署に相談してみるのも良いかもしれません。
【死別後2年以内に必要なこと】
〇生命保険の請求
一般的には、死亡給付金請求書、保険証券、死亡診断書、住民票、受取人の印鑑証明書、受取人の戸籍謄本などの準備が必要です(商法上2年以内、3年以内の保険会社も多い)。
〇高額医療費の申請
なくなられた方に必要とした医療費で一定の自己負担額を超えた金額について申請出来ます(支払後2年以内)。
〇健康保険の埋葬料の申請
被相続人が被保険者の場合は、年金事務所や健康保険組合で手続が出来ます(死亡後2年以内)。
〇国民健康保険の葬祭費の申請
被相続人が被保険者の場合は、役所で手続が出来ます(葬儀後2年以内)。
【死別後5年以内に必要なこと】
〇国民年金・厚生年金・共済年金の遺族年金などの請求
役所や年金事務所、共済組合事務所で手続きが必要です。手続きの期限に猶予がありますが、できるだけ早めに行いましょう。
【気持ちの整理の過程で】
〇遺品の整理
49日が過ぎてからと言われたりしていますが、整理をすることによって、その方と過ごした日々が赤裸々によみがえり、つらくなるかもしれません。急ぐ必要はないと思われます。
〇納骨
一般的には1周忌頃とも言われていますが、ご自身が納得されることが大切です。家族、親族、宗教関係者とも相談し、適切な時期を導き出して頂けたらと思います。
東日本大震災の追悼式情報は、毎年、3月上旬に掲載しています。
下記は、2024年の追悼式情報です。
《 福島県 》
福島県 東日本大震災追悼復興祈念式
【日時】令和6年3月11日(月) 14:30~15:40
【場所】パルセいいざか(福島市飯坂町字筑前)
いわき市 令和6年いわき市東日本大震災追悼式
【日時】令和6年3月11日(月)14:45~
【会場】いわき芸術文化交流館アリオス 中劇場(いわき市平字三崎)
双葉町 令和6年東日本大震災双葉町追悼献花場
【日時】令和6年3月11日(月)9:00~16:00
【会場】双葉町産業交流センター 大会議室(双葉町大字中野字高田)
大熊町 3.11のつどい
【日時】令和6年3月11日(月) 14:00~
【会場】大熊町役場前広場(大熊町大字大川原字南平)
浪江町 令和5年度浪江町東日本大震災追悼式
【日時】令和6年3月11日(月) 14:40~15:40
【会場】如水典礼さくらホール(浪江町大字高瀬字原田2)
【参照】広報なみえ(2024年2月号 P23)
楢葉町 3.11・つなぐ・未来。
【日時】令和6年3月11日(月) 10:00~18:00
【会場】ここなら笑店街 中央広場
【参照】広報ならは(2024年2月 P18)
相馬市 相馬市東日本大震災追悼式
【日時】令和6年3月11日(月) 14:35~
【会場】市民会館
【参照】広報そうま(2024年2月15日号 P1)
南相馬市 令和5年度南相馬市東日本大震災追悼式
【日時】令和6年3月11日(月) 13:30~16:00
【会場】南相馬市民文化会館「ゆめはっと」大ホール(南相馬市原町区本町)
広野町 東日本大震災追悼献花
【日時】令和6年3月11日(月) 14:00~15:00
【会場】震災記念公園(広野町大字下浅見川字本町地内)
富岡町 富あかり2024
【日時】令和6年3月11日(月) 18:00~20:00
【会場】富岡町立富岡第一小学校跡地
《 岩手県 》
岩手県 岩手県東日本大震災津波追悼式
【日時】令和6年3月11日(月) 14:40~16:00
【会場】トーサイクラシックホール岩手(岩手県民会館)中ホール(盛岡市内丸)
盛岡市 東日本大震災13周年行事「祈りの灯火2024~記憶を語りつぐ日~」
【日時】令和6年3月11日(月) 14:40~19:00
【会場】盛岡城跡公園(もりおか歴史文化館前広場)他
大槌町 令和5年度大槌町東日本大震災津波追悼献花
【日時】令和6年3月11日(月) (追悼式)14:30~15:30(献花)9:00~12:00、16:00~17:00
【会場】大槌町文化交流センター「おしゃっち」多目的ホール(上閉伊郡大槌町末広町)
釜石市 東日本大震災犠牲者追悼式
【日時】令和6年3月11日(月) 14:45~15:15
【会場】釜石祈りのパーク(釜石市鵜住居町)
【参照】広報かまいし(2024年3月1日号 P2)
大船渡市 令和5年度東日本大震災大船渡市犠牲者追悼式
【日時】令和6年3月11日(月) 14:25~15:15
【会場】みなと公園展望広場 (祈りのモニュメント前)
陸前高田市 東日本大震災追悼式
【日時】令和6年3月11日(月) 14:40~15:30
【会場】市民文化会館 奇跡の一本松ホール(陸前高田市高田町字館の沖)
山田町 東日本大震災・大津波 山田町犠牲者十三周年追悼式
【日時】令和6年3月11日(月)14:40~15:30
【会場】山田町中央公民館 大ホール(下閉伊郡山田町八幡町)
宮古市 宮古市東日本大震災追悼式
【日時】令和6年3月11日(月)14:30~16:30
【会場】宮古市民文化会館(宮古市磯鶏沖)
遠野市 東日本大震災犠牲者追悼サイレンの吹鳴
【日時】令和6年3月11日(月)14:46
【会場】市内にて追悼のサイレンを鳴らします
野田村 東日本大震災追悼行事
【日時】令和6年3月11日(月)14:00~15:00
【会場】東日本大震災大津波記念碑前(十府ヶ浦公園ほたてんぼうだい付近)
【参照】広報のだ(令和6年2月号 P12)
《 宮城県 》
宮城県 みやぎ鎮魂の日
【日時】令和6年3月11日(月)9:00~17:00
【会場】宮城県行政庁舎2階講堂(仙台市青葉区本町)
仙台市 仙台市 東日本大震災仙台市追悼式
【日時】令和6年3月11日(月)14:30~16:00
【会場】新田東総合運動場 宮城野体育館(宮城野区新田東)
石巻市 東日本大震災石巻市追悼式
【日時】令和6年3月11日(月)14:40~16:00
【会場】石巻市慰霊碑(石巻南浜津波復興祈念公園内)
塩竃市 東日本大震災塩竈市追悼献花所
【日時】令和6年3月11日(月)13:00~16:00
【会場】千賀の浦緑地内 東日本大震災モニュメント前(地番:海岸通196番4)
気仙沼市 令和6年気仙沼市東日本大震災追悼と防災のつどい
【日時】令和6年3月11日(月)10:00~19:00
【会場】気仙沼中央公民館(気仙沼市内の脇)
名取市 東日本大震災名取市追悼献花
【日時】令和6年3月11日(月)9:00~16:00
【会場】
・市役所1階市民ホール(名取市増田字柳田)
・名取市震災メモリアル公園慰霊碑(名取市閖上東)
多賀城市 東日本大震災多賀城市追悼行事
【日時】令和6年3月11日(月)11:00~15:00
【会場】多賀城駅前公園(JR仙石線多賀城駅南側)
岩沼市 東日本大震災追悼行事「希望の灯火(あかり)」
【日時】令和6年3月10日(日)17:00~19:00
【会場】千年希望の丘 相野釜公園
自由献花台の設置
【日時】令和6年3月11日(月)10:00~16:00
【会場】千年希望の丘 相野釜公園
東松島市 令和6年東日本大震災東松島市追悼式
【日時】令和6年3月11日(月)14:30~15:30
【会場】東松島市コミュニティセンター(東松島市矢本字大溜)
亘理町 東日本大震災亘理町追悼献花
【日時】令和6年3月11日(月)8:30~17:00
【会場】亘理町役場 多目的ホール (亘理町字悠里)
山元町 東日本大震災13周年追悼行事
【日時】令和6年3月11日(月)10:00~16:00
【会場】慰霊碑「大地の塔」(旧JR山下駅跡地)
七ヶ浜町 日本大震災追悼行事 自由献花
【日時】令和6年3月11日(月)12:00~16:00
【会場】
・七ヶ浜町公園墓地〈蓮沼苑〉東日本大震災慰霊碑前(七ヶ浜町代ヶ崎浜字蓮沼)
・七ヶ浜国際村エントランス入口(七ヶ浜町花渕浜字大山)
利府町 東日本大震災犠牲者の追悼「みやぎ鎮魂の日」 サイレン音を鳴らします
【日時】令和6年3月11日(月)14:46
【場所】町内各所に設置している防災行政無線で、サイレン音を1分間鳴らします
【参照】 広報りふ(2024年3月 P6)
女川町 女川町追悼のつどい
【日時】令和6年3月11日(月)9:00~16:00
【会場】東日本大震災慰霊碑前(役場敷地内)
【参照】広報おながわ(2024年3月号 P8)
南三陸町 令和6年東日本大震災追悼行事
【日時】令和6年3月11日(月)13:00~18:00
【会場】南三陸町総合体育館(ベイサイドアリーナ 文化交流ホール)
松島町 献花台
【日時】令和6年3月11日(月)13:00~16:00
【会場】東日本大震災慰霊記念碑前(県営第1駐車場五大堂側)
【参照】広報まつしま(2024年3月号 P9)
〇あいまいな喪失情報ウェブサイト
〇ストレス・災害時こころの情報支援センター
https://saigai-kokoro.ncnp.go.jp/
〇亡くなった方へのメッセージプロジェクト フォーエバープロジェクト
https://www.forever-net.com/top.php
〇NPO法人仙台グリーフケア研究会
〇NPO法人子どもグリーフサポートステーション
〇関西遺族会ネットワーク
〇あかさかグリーフカフェ:wind
https://www.iuhw.ac.jp/daigakuin/soudan/
〇グリーフサポートリンク(自死遺族の方)
一方、「喪失」の問題は、家族や家、仕事、家財、住み慣れた町並みや近隣の人々など、自分にとってかけがえのない大切な人やものを失った悲しみからくるものです。
以下では、災害で大切な人を失った方に起こる心の問題をまとめてみました。
【災害後の感情】
【その他のこと】
以上のことは、非常に苦痛を伴いますが、それらは喪失やトラウマ体験に対する正常な反応です。その人が弱いからでも、悪かったわけでもありません。
災害は、人の人生を脅かします。どのような状態になっても、全く不思議ではありません。あなたが弱いからコントロールできないのでも、何かあなたに責任があってこのようなことが起こったのでもありません。
「トラウマ」の問題も、「喪失」の問題も、人によってそれらが及ぼす影響や、それに対する対処方法はさまざまです。これが「正しい」反応の仕方、対処は「こうするべき」、というものはありません。すべての人にとって、悲しみも、悲しみ方も異なっています。
また、悲しみのプロセスには、時間が必要です。数ヶ月で気持ちが楽になる人もいれば、数年かかることもあるでしょう。人と比較せず、自分のペースで、少しずつ元気になっていくことが大切です。
しかし、いつまでも圧倒され、何ヶ月間も日常生活を送ることに支障が出る場合、あるいは何か気がかりな問題が解決できないまま続く場合、生きていても仕方がないと思う気持ちが何度もわきあがる場合には、心の専門家(精神科医・心療内科医・心理職など)や遺族の支援団体、支援機関、かかりつけ医などに相談してみましょう。